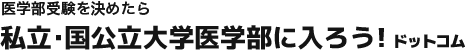医学部受験の化学学習法 第5回
さらに上位レベルへ
<1>文章読解型
東大を筆頭に、国立上位大学に多いタイプの問題です。題材は、1世紀以上前の論文や書籍、比較的最近の研究、大学で用いるようなテキスト…とさまざまです。ただし、それらに関する知識を必要とする問題ではなく、高校内容を学習していれば、文章を読んで理解できるようになっています。
基本的に特別な対策は必要ありませんが、新聞・雑誌(『日経サイエンス』など)・書籍(文庫本でもよい)で、興味があるものを日常的に読むのもお勧めです。読んで得る知識が直接対策になるわけではなく、専門性のある文章を読む練習と考えましょう。
<2>実験考察型
頻出タイプの実験に関しては、問題集などで練習するのが対策になりますが、国立上位大学や医学部単科大学では、初めて見るような実験についても出題されます。問題文を読んで理解するという点では、『1.文章読解型』と同様ですが、実験結果から考察、推測する必要があるため、難易度が高くなります。自分の持つ知識を総動員して考えることになります。
<3>高校範囲外の理論
電子軌道の理論、化学平衡の扱い、有機反応論など、大学で習う理論に関する問題ですが、一部の医学部単科大学を除いて、出題されません。出題されているように見えても実は『1.文章読解型』で、読めば分かるように設定されています。
気になる人、興味がある人は、駿台文庫石川正明先生の著書(『化学の発想法』など)を読んでみましょう。といっても、それらの本に書いてある知識が直接入試の得点になるわけではありません。これまで理屈抜きで覚えていた事柄に関して、統一された理論を導入することで新たな視点が得られ、より深い学習ができるというのが目的です。
<4>知識型
化学史上の人物、化学物質の利用法、生化学に関連する物質など、通常の入試で出題される内容を逸脱した知識を問う問題です。興味がある分野について調べてみるのはよいことですが、得点源にはなりません。もし出題されても捨ててください。
難問と考えられるのは、だいたい以上に分類できます。簡単に対処する方法はありませんが、日常的に自然科学に興味をもって接することは、受験後にも役立ちます。
いずれにしても、難問が出題される大学は限られていますので、過去問はチェックすること。場合によっては、その出題傾向によって受験する大学を決めてもよいかもしれません。
最後に
高校生にもなれば、それぞれが持っている能力の差は非常に大きいと言わざるを得ません。受験で重要な能力の中には、残念ながら今更あまり伸びない種類のもの(ひらめき、空間把握、頭の回転の速さ…)もありますが、高校生になってから伸びるもの(論理性、思考の長さ、知識を整理する力…)もあります。自分の持っている能力を発揮できるように、伸ばすことができる能力を受験勉強の間にも伸ばせるように、個性を生かした学習をし、実りの多い受験生活を送ってください。
医学部受験の化学学習法 記事一覧
- はじめに
- 偏差値50まで
- 偏差値50まで(理論化学)
- 偏差値50まで(無機化学・有機化学)
- さらに上位レベルへ