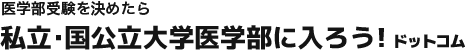金沢医科大学 一般入試 物理
金沢医科大学の理科は二科目合わせて120分。単純計算で一科目あたり60分の計算である。
問題形式について
まず大問について。
2008年度から2012年度までの5年間では、2008年度だけが6問で、2009年度からは4問という構成になっていた。おそらく2013年度以降も4問というのは守られると思う。そうすると、大問1問あたりにかけられる時間は平均して15分となる。
次に小問について。
記述は全く無く、全て選択の穴埋め式となっていた。これはおそらく今後も崩れる事はまず無いだろうと思う。
大問1問あたりの小問数は、少ないもので3問、多いもので13問と非常に幅広かった。といっても少ない物は少ないだけ一つ一つが比較的重く、多いものでは穴埋めが答えの一部の指数だけだったりするなどがあった。しかし選択式というのは5年間一貫していて、記述式は一度も出なかった。
以下に各大問あたりの小問数の表を示す。
| 年度 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小問数 | 第1問 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 第2問 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
| 第3問 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | |
| 第4問 | 13 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| 第5問 | 5 | |||||
| 第6問 | 6 | |||||
| 合計 | 32 | 28 | 29 | 29 | 33 | |
| 平均 | 8 | 7 | 7.25 | 7.25 | 5.5 | |
次に、大問あたりの小問数とその出題回数の表を示す。
| 小問数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題回数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
上の表を見ると、年度毎に合計の小問数は大きく変化していない事がわかる。また、全体で見ても年度ごとで見ても大問ごとの小問数はばらばらで、小問数がいくつの問題が最も出やすい、というのはわからない事がわかる。
物理にかけられる時間が60分である事から、小問1問あたりにかけられる時間は、小問数の最も多い2008年度で1.8分、最も少ない2011年度で2.1分だった。5年間で合計で出題された小問は151問である事から、5年間合計で小問1問あたりにかけられる時間は2.0分となった。なので、大体小問1問を2分前後で片付けようという意気込みでよいだろう。
ただし、上にも書いたが小問によって重さが段違いなので、もちろん時間をかけなければならないものもあるし、逆に見てすぐわかるものだったり、2つ以上の穴が一度に埋まったりするものもある。あくまで平均して2分という事は心に留めておいた方がいいかもしれない。
しかしまあこれだけ大問毎に小問数にばらつきがあり、また重さも千差万別だと、小問1問あたり2分というよりは、大問1問あたり15分という目安で取り組んだ方がよいかもしれない。その場合、小問数が13問と最も多い問題では小問1問あたりにかけられる時間は1.2分、小問数が3問と最も少ない問題では5分といった所だろうか。
出題範囲について
以下に、年度・問題別の出題範囲の表を示す。
| 第1問 | 第2問 | 第3問 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 力学 |
等速円運動 水平投射 |
電磁気 | 非線形抵抗 | 力学 | 二物体の運動 衝突 |
| 2011年度 | 力学 |
二物体の運動 衝突 |
熱力学 | 熱機関 | 電磁気 | コンデンサー(回路) |
| 2010年度 | 電磁気 | 電荷の運動 | 電磁気 | クーロンの法則 直線電流による磁場 |
熱力学 | 2つの容器内の気体 |
| 2009年度 | 電磁気 | コンデンサー(回路) | 波動 | 回折格子 | 力学 | 相対速度 斜方投射 定圧変化 |
| 2008年度 | 波動 | ドップラー効果 | 原子物理 | 電磁気 | 磁場中の導体棒 | |
| 第4問 | 第5問 | 第6問 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 電磁気 | 電荷による電場 | ||||
| 2011年度 | 波動 |
|||||
| 2010年度 | 力学 | 斜面での運動 衝突 |
||||
| 2009年度 | 力学 | ばね 衝突 |
||||
| 2008年度 | 熱力学 | 熱機関 | 力学 | 斜方投射 水平投射 |
力学 | ばね 等速円運動 |
まず、2010年度の第2問など、一部二つ以上の分野に跨って出題されている問題がいくつかあった。そういった問題は、私がよりメインだと考える方の分野の問題としておいた。
この表を見ると、どの年度も力学と電磁気の問題は含んでいる。上で説明したように一部電磁気の事柄が他の範囲に跨って出題されている問題もあるが、大体電磁気は一年度で1問、力学は2問で、残りの1問が熱力学か波動か、といった所だろうか。しかし2012年度のように、波動、熱力学の問題が出ない年度もあった。この年度は力学や電磁気メインで波動や熱力学を扱ったという事も全く無く、これらの分野の内容は全く出る事は無かった。意図して出さなかったのか、たまたまなのかはわからないが、2013年度以降はどうなっていくのか、という事は正直言ってまだ読めないと思う。少なくとも今年度に波動、熱力学の分野を取り扱わなかったからといって対策しなくてもよいという訳ではないので、むしろ両方出るくらいの気持ちで準備していくべきだと思う。
問題について
まず、全体を通した雑感について。
記述が全く無く、全て選択式の問題だった。これは最初に取り組んだ時に一目でわかる事だが、その時に思った事は、折角選択式なのだから、一つ一つ記述のようにきちんと計算をして答えを出して選ぶというのは損だな、という事である。例えば聞かれているのが速度だったら選択肢それぞれの単位だけ計算して速度になっていないものはそこで切る、残った選択肢の違う部分を見てその部分が計算ではどうなるのかといった事のみに絞って計算する、など、真正面から計算せずにより計算量を少なく、早くやる方法はある。もちろんこれが出来るようになるまでは多少訓練が必要だとは思うが、こういったやり方に加えて普通に計算する事もすればそれだけミスは少なくなるし、万が一時間が足りなくなりそうだという時に勘で答えるのではなく少しでも選択肢を絞って当たる確率を挙げられるので、出来ればかなり得なやり方だと思う。この大学を受験しようという人には、ぜひ身につけて欲しい。
次に、各年度について書いていこうと思う。
2012年度
全体
全体的な難易度は例年通り。第1問が数値計算もあり他の3問よりも計算量も多く、ここでミスをしてしまうかもしれない。しかし他の3問が比較的簡単なのでそこで十分にカバーできると思うので、第2問以降はしっかり取ろう。
第1問 力学 等速円運動 水平投射
難易度はやや高め。円錐振り子についてと、水平投射について考察する問題。(2)に数値計算があり若干鬱陶しい部分もあるが、そもそも穴埋めが4つしか無いので、1問あたり3分かけても大丈夫。落ち着いて計算しよう。(3)は、上で説明したような単位計算などをして絞っていく方がいいと思う。ここでは、![]() の単位を考えてみて欲しい。ここで問われているのは距離なので、もちろん答えの単位はmである。
の単位を考えてみて欲しい。ここで問われているのは距離なので、もちろん答えの単位はmである。![]() にはルートがついているので、
にはルートがついているので、![]() の単位はm2となるはずである。しかし、そうはならない。なので、一見複雑で答えっぽそうは雰囲気を出してはいるものの、これを含む③④⑦⑧は答えではないと判断できる。ここではこれ以上は書かないが、残った①②⑤⑥は選択肢を見て「rは混合の中に入るのかどうか」という事と、「
の単位はm2となるはずである。しかし、そうはならない。なので、一見複雑で答えっぽそうは雰囲気を出してはいるものの、これを含む③④⑦⑧は答えではないと判断できる。ここではこれ以上は書かないが、残った①②⑤⑥は選択肢を見て「rは混合の中に入るのかどうか」という事と、「![]() の係数は1なのか2なのか」という事に絞って計算するのがよいだろう。
の係数は1なのか2なのか」という事に絞って計算するのがよいだろう。
第2問 電磁気 非線形抵抗
難易度はやや低め。非線形抵抗を含む回路について考察する問題。まず選択肢だが、この問題は電源の起電力や抵抗の抵抗値を数値として与え、また選択肢の数値のみなので上で説明したような単位などで切るやり方は使えないだろう。これは一つ一つ計算するしかないと思う。この問題は、回路によって非線形抵抗にかかる電圧、電流を式にして表し、それを与えられた非線形抵抗の電流、電圧図に書き込んで交点を求めて電流、電圧を求めるというオーソドックスなやり方で全て解ける。これはミス無く全て取りたい。
第3問 二物体の運動 衝突
難易度は低い。静止している物体に別の物体を衝突させ、その後の運動を考察する問題。13~15はただ運動量保存則の穴埋めをして16~19はただそれを計算するだけという、非常に簡単な問題。この問題で差がつく事は恐らく無いので、絶対に解けなければいけない問題だと思う。
第4問 電磁気 電荷による電場
難易度は普通。点電荷によって作られる電場、またその電場による電位について考察する問題。教科書に間違いなく載っているような問題なので、全て完璧にとは言わないがかなり良い所までは解けていて欲しい。
2011年度
全体
全体的な難易度は例年通り。第4問が他に比べて難易度が少し高いと思うが、その分他の問題がしょっちゅう目にするような典型問題ばかりなので、その3問で稼げるだけ稼いで第4問は解ける所まで、というのが合格点を最も取りやすい配分だと思う。また、第2問などはおそらく15分かかからないはずなので、余った時間を第4問や他の問題にまわすなどを考えた方がいいだろう。
第1問 二物体の運動 衝突
難易度は普通。物体を射出すると同時にもう一方の物体を自由落下させ衝突させる、という問題である。この問題は一般にはモンキーハンティングと呼ばれ、本問でいう物体Aを弾丸、物体Bを猿にみたてた時、弾丸を当てるたまには撃つ人は初めどのような角度で打ち出せば良いか、という事を考察するための問題である。残念ながら本問ではそこは問われていないが、実は最初に物体Bの方向を向けて打ち出せば必ず当たるのである。今回のケースだと水平距離L、高さLなので仰角45°で打ち出している、という事になる。これは本問とは直接関係の無い事だが、知っていても損はないと思うので説明しておいた。衝突までは自由落下と斜方投射、衝突の瞬間は運動量保存、衝突後は斜方投射をきちんと別々に式を立てて考えて解こう。
第2問 熱機関
難易度はやや低め。定圧変化、定積変化のみで構成された熱機関について考察する問題。定圧変化、定積変化はP-Vグラフではどちらも軸に平行なグラフの変化となるので、等温変化や断熱変化が含まれる熱機関よりもはるかに考えやすくなっている。小問数も少なく、また一つ一つの問題もさほど重くは無いので、これは出来れば10~15分で完璧に解きたい問題である。
第3問 コンデンサーを含む回路
難易度は普通。複数のコンデンサーとスイッチを含む回路について考察する問題。こういった問題で必ず考えなければならないのは、①電荷保存則、②キルヒホッフの法則、③コンデンサーの基本式Q=CV、の3つである。この3つを使いこなせれば大概の問題は解く事ができる。あとはこの問題で問われているようにコンデンサーの静電エネルギーが![]() と与えられる事くらいだろうか。とにかくこういった問題は必ず一度はやった事があるはずなので、7割から8割は解けていて欲しい。
と与えられる事くらいだろうか。とにかくこういった問題は必ず一度はやった事があるはずなので、7割から8割は解けていて欲しい。
第4問 波動 ドップラー効果
難易度はやや高め。観測者を含まない直線上を運動する音源について考察する問題。公式を用いて解くのではなく、ミクロな視点から考察を加えていき、結論として観測者が観測する振動数はどうか、という事を考える問題となっている。他の問題が割と典型問題だったのに対し、こういった問題をこれまでにやった事があり、しかも対策もしっかりできているという人は少ないのではないかと思う。それほど多くはないものの誘導もついているので、それに乗れるだけ乗って解ける所まで解くといった所でよいだろう。
2010年度
全体
全体的な難易度はやや高め。例年1問はあるようないわゆる取り問が無く、また第1問、第4問の難易度が高いので苦しんだ受験生は多いと思う。この年度ならば第2問、第3問は取りたい。第1問は単位計算のみで絞れるものも多いので、そこで時間短縮して第4問にその分時間を割こう。
第1問 電磁気 電荷の運動
難易度はやや高め。電荷を電源で加速し、磁場の中を通らせ、電場で曲げるという、総合的な問題。総合的な力が問われるのでどこか一つが欠けていたらアウトというような問題である。その上問題数も多いので、苦しむ受験生も多いのではないかと思う。しかし単位のみを計算して答えが一つに絞られるものも少なくないので、真正面から計算せずにまず選択肢を絞る、という事が重要になってくると思う。
第2問 クーロンの法則 直線電流による磁場
難易度は普通。前半はクーロンの法則を用いて電荷の大きさをおもめ、後半は直線電流によって作られる磁場を求める問題。前半は電磁気の問題とはいってもかなり力学チックな所があり、題材として電荷が用いられているだけ、と言った方が正しいかもしれない。後半は前半とは関係がなく、公式と磁場の重ね合わせだけできれば解けてしまう問題である。後半は公式を知らなかったり忘れていたりしたら手がつけられないので、公式はきちんと暗記して臨もう。
第3問 熱力学 2つの容器内の気体
難易度は普通。管で連結された2つの理想気体について考察する問題。小問数が3問とここ5年間で2008年度の第1問と並んで最も少ない。それだけに1問1問は比較的重いので、ここは少し時間をかけてもいい部分だと思う。体積、圧力、温度、気体定数を与えて物質量を求められたりする部分など、明らかに気体の状態方程式を使ってくれと言わんばかりである。19を見ると選択肢がどれも複雑で、計算が煩雑だろうなとは予想がつく(実際そうなのだが)ので、自分の計算力に自信が無く少し時間が足りないと思ったらここ早々に見切りをつけるのも一つの手だと思う。
第4問 力学 斜面での運動 衝突
難易度は高い。まず斜面上を物体が動き、その後小球と衝突してその後は小球と床との衝突を考える問題。まず選択肢を見ればわかるが、ほとんどが数値計算である。しかも近似も求められているので、計算量は更に増え、正確さも求められる。小問数も10問と多い方で一つ一つが重いので、これらを時間内に完答するのはなかなか難しいと思う。少なくとも解答のように計算するのではなく、例えば26は反発係数が0.6である事を踏まえてこの26の答えの2倍の0.6倍つまり1.2倍がEFの距離0.6mであると考えて、26の答えは0.5mである、と出すようなやり方はしなければならないと思う。
2009年度
全体
全体的な難易度は例年通り。ただ例年は大問ごとに難易度に多少偏りがあるが、今年度の問題に関してはそれはあまり見られなかったように思う。とにかく自分に得意な所から手を付けていくというのが最も高得点を取れる戦略だと思う。
第1問 電磁気 コンデンサーを含む回路
難易度は普通。スイッチとコンデンサーを複数含む回路について考察する問題。2011年度の第3問の説明と同じように、コンデンサーの基本式、電化保存則、キルヒホッフの法則の3つを用いれば、あとは計算力の問題になるはず。コンデンサーの電気容量や抵抗の抵抗値も与えて求める値を具体的な数値として求めさせているので、単位計算で絞るという事はできないだろう。しかし、そんな事をしなくてもこれはそう難しい問題ではないと思うので、普通に計算しても全て解けるくらいの実力は身につけていて貰いたい。
第2問 波動 回折格子
難易度は普通。一般的な回折格子について考察する問題。これも具体的な数値計算があり、きちんと計算をやらなければいけないので選択式というのがあまり生かされず残念である。それでも、例えば15は屈折率1.5の媒質を入れたのだから、明線間隔は13の答えの ![]() 倍になるという事に気付けば答えはすぐわかる。
倍になるという事に気付けば答えはすぐわかる。
第3問 力学 相対速度 定圧変化
難易度は普通。(1)は流れのある川と船について考察する問題。(2)は物体の斜方投射について考察する問題。(3)は理想気体の定圧変化について考察する問題。小問集のような大問である。(3)は明らかに熱力学の問題だが、(1)(2)が力学の問題なのでメインは力学という事で力学の大問と分類した。(1)は物理Ⅰの最初の方で習うような内容で、受験期にあまり触れる機会は無いかもしれないが、これは時間を設定するなりして自分だけの力でも解けてほしい。(2)は鉛直投げ上げと、斜方投射の問題。(3)は、定圧変化の時の気体の仕事を計算させる問題である。定圧変化なので、仕事はPΔVでよい。あとはΔVを求める事を考えよう。
第4問 力学 ばね 衝突
難易度は普通。ばねによって加速された物体と、それが衝突して単振動する別の物体について考察する問題。答えとして求められているのは全て係数を計算すればよいだけなので、全部丁寧に計算するのではなく文字は置いといて係数だけ計算するようにするのが時間的にベストな選択だと思う。
2008年度
全体
全体的な難易度は例年通り。他の4年間よりも大問数が2問多くなっているが、その分1問1問の量は少ない。また、年度の新しいものは選択肢が文字式である物の方が多かったのに対し、この年度の選択肢はほとんどが数字だった。なので、大問数の観点から言っても、選択肢の観点から言っても、最新のものとは別の大学のものと言っていい程違った形式をとっているように思う。
第1問 波動 ドップラー効果
難易度は普通。図を見ながらドップラー効果について考察する問題。ぱっと公式を用いて振動数などを計算する事はできないようになっているので、きちんと誘導に乗りながら自分で一つ一つ考えなくてはならない。頭ごなしに公式を暗記して臨んでいる人はなかなか手が出せなかっただろうと思う。なので、こういった問題を見て、問題を覚えるのではなく自分で考える力も求められているのだなという事がわかる。
第2問 原子物理
原子物理の範囲は現課程では出ないので省略する。
第3問 電磁気 磁場中の導体棒
難易度は普通。磁場中にある導体棒について、最初は磁場が変化し、その次は磁場はそのままで導体棒を運動させて考察する問題。前半も後半も結局の所、抵抗と導体棒で囲まれた部分を貫く磁束が変化する事について考えるという同じ事をしているだけだと気付けば、前半も後半も解けるはずである。この問題でも具体的な数値計算が求められているので、計算ミスだけはしないように注意したい。
第4問 熱力学 熱機関
難易度はやや低め。熱機関について考察する問題である。定圧変化、等温変化、定積変化を全て含む最もポピュラーな熱機関だと思う。ここで求められているのは温度と、定圧変化・定積変化の部分のみの気体に入る熱量や、仕事なので、等温変化の部分はあまり関係が無くなってしまっているが、それはおそらく気体が等温変化の部分でする仕事を計算するのがかなりレベルが上がって難しくなるからだと思う。これをもし求めようと思ったら、等温変化の部分の圧力を体積で積分した値が仕事になるのでlogが出てきて難易度が一気にぐっと上がる。本問ではそれは無いので、比較的単純な問題だと思う。
第5問 力学 斜方投射 水平投射
難易度は普通。前半は物体の斜方投射、後半は水平投射について考察する問題。問題設定自体は実に単純だが、求められるのが高さ、時間、運動量、運動エネルギーとバラエティに富んでいる。といっても運動量、運動エネルギーが何たるかくらいを知っていれば難無く通過できる。これも数値計算が求められる。
第6問 力学 ばね 等速円運動
難易度はやや低め。前半はばねの釣り合い、後半はばねの片端を中心とした等速円運動について考察する問題。ばねがある長さ以上になると切れてしまうという設定を持ってきてそれについて考えさせるのは珍しいなという印象だったが、かといって難易度が上がったかといえばそうでも無かった。しかもこの問題はどれも係数を答えさせるのみなので、係数にのみ注目して式を解けばより早く解答が出せると思う。