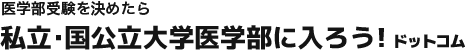兵庫医科大学 一般入試 物理
兵庫医科大学の理科は二科目合わせて120分。単純計算で一科目あたり60分の計算である。
問題形式について
まず大問について。
大問数は、2008年度は3問、2009年度は4問、2010年度は5問、2011年度は4問、2012年度は3問と、年度ごとにばらばらである。形式が変わったというレベルの変化ではないので、2013年度以降がどうなるかという事は正直何とも言えないが、この規則性に従うならば4問、その次が5問なのだろうか。物理にかけられる時間を60分だとすると、大問1問あたりにかけられる時間は3問ならば20分、5問ならば12分となる。
次に小問について。
大問は(1)、(2)、・・・と分かれているものもあれば、穴埋めとなっている物もある。どちらも求められている事柄はそう変わらないが。しかし2010年度の第4問は5年間でも異色で、小問に分かれる事は無く、答えとして求められるものは一つで、その道筋まで記述で示せ、というものであった。文章中で使う単位を明示しながら定義する、などかなりの記述力を求められる物であった。2011年度、2012年度はそういった問題は出ていないが、2013年度にまたこのような問題が出題される可能性はあると思うので、きちんとした記述力も必要になってくると思う。
以下に各大問あたりの小問数の表を示す。ただし、2010年度の第4問は1問とカウントした。
| 年度 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小問数 | 第1問 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
| 第2問 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 第3問 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | |
| 第4問 | 11 | 1 | 4 | |||
| 第5問 | 3 | |||||
| 合計 | 31 | 32 | 21 | 26 | 26 | |
| 平均 | 10.3 | 8 | 4.2 | 6.5 | 8.7 | |
上の表を見ると、年度ごとに出題されている小問の数は増加傾向にある事がわかる。これは同じ問題数の2012年度と2008年度、2011年度と2009年度を比較してみてもわかる。また、大問1問ごとの平均小問数は、2010年度から目に見えて増加している。しかしこれ以上増加すると60分で解き終わらなくなると思うので、ここからさらに増加していくという事は考えにくい。
小問1問あたりにかけられる時間は、小問数の最も多い2011年度で1.9分、最も少ない2010年度で2.9分だった。また、5年間で合計で出題された小問は136問だったので、1年度あたりに出題される小問の平均は27問で、この場合小問1問あたりにかけられる時間は2.2分となった。なので、小問1問を大体平均して2~3分で片付けよう、という意気込みで取り組めばよいと思う。もちろん小問ごとにばらつきはあるので、早いのもは1分以内に片付けてその時間を他の問題にまわしたい。
出題範囲について
以下に、年度・問題別の出題範囲の表を示す。
| 第1問 | 第2問 | 第3問 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 小問集 | 力学 | 斜面での運動 摩擦 衝突 |
電磁気 | コンデンサー(回路) | |
| 2011年度 | 小問集 | 電磁気 | 電荷の運動 | 熱力学 | 気体分子運動論 | |
| 2010年度 | 小問集 | 力学 | ばね 単振動 |
熱力学 | 等温変化 定圧変化 |
|
| 2009年度 | 小問集 | 力学 | 定滑車 動滑車 |
電磁気 | 半導体 | |
| 2008年度 | 小問集 | 力学 | ばね 単振動 |
電磁気 | 磁場中の導体棒 摩擦 |
|
| 第4問 | 第5問 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | ||||
| 2011年度 | 電磁気 | 半導体 ダイオード |
||
| 2010年度 | 熱力学 | 比熱 | 電磁気 | 磁場中の電荷 等速円運動 |
| 2009年度 | 波動 | 正弦波 | ||
| 2008年度 | ||||
例年第1問は小問集となっていた。小問集のおおまかな範囲については、各年度の問題についての部分で触れる事にする。
上の表を見ると、電磁気は毎年1問は出ていたが、2011年度は力学の大問は出題されなかった(実は第2問が電磁気の分野で扱いつつも内容は力学の割合が多かったが)。他の大学では大体毎年力学と電磁気は出題され、大問数に応じて残りの問題に波動や熱力学、といった感じだったのでこれは珍しい事だと思った。また大問数が4問、5問の年度は、そこに電磁気あるいは波動、熱力学の問題が入る事がわかる。しかし2011年度のように電磁気が入ったり、2010年度のように熱力学の問題を2問出題したりなど、あまりバランスよく、といった配置はされていないように思う。
電磁気の問題では、5年間で出題された6問中2問は電荷の運動について、2問は半導体についてだったので、この大学はこの二つの分野を好んで出す傾向があるのかなと感じた。特に半導体については、高校物理では扱うものの大学受験ではあまり出題されない範囲なので、一般的な受験生できちんと対策をしている人は少ないと思う。この大学を受験したいと考えているならば、半導体はしっかり勉強しておこう。
問題について
まず、全体を通した雑感について。
他の大学とここが違うなと感じた所は、第1問の小問集である。ここには誘導はあまり無く、きちんと公式や概念を覚えているかどうか、の確認程度の問題ばかりなので、しっかり取って欲しい部分だと思う。
次に、各年度について書いていこうと思う。
2012年度
全体
全体的な難易度は例年通り。大問数が同じ2008年度と第1問の小問集の小問の数も同じである。小問集は、普通の大問のようにどこかがわからなくなったらその先はほとんど取れない、という事が無いのでその割合が高い事は受験生にとってはありがたい事のはずなので、第1問は8割くらいはしっかり取って欲しい。第2問、第3問は途中から解けなくなるという事が考えられるので、小問集で8割くらい、第2問、第3問で7割前後を取れば十分合格点には届くと思う。
第1問 小問集
(1)は波動、正弦波の分野から、固定端での反射波を図示する問題。
(2)は波動、電磁波の分野から、X線などの電磁波を波長順に並べる問題。
(3)は波動、正弦波の分野から、条件から波の振動数を求める問題。
(4)は力学、ばねの分野から、条件からばね定数を求める問題。
(5)は力学、浮力の分野から、媒質中の物体を静止させるのに必要な力を求める問題。
(6)は電磁気、電場の分野から、ある条件下での電位のグラフを書く問題。
(7)は電磁気、自己誘導の分野から、ある条件下での磁束密度の変化量を求める問題。
(8)は熱力学、比熱の分野から、水の状態変化に必要な熱量を求める問題。
(9)は熱力学、気体の分野から、管で繋がれた2つの容器内の気体についての問題。
(10)は原子物理、発光ダイオードの分野から、ある条件下での光の波長を求める問題。
難易度は普通。大問が3問と少ないだけに第1問の小問集の問題数は2008年度と同じように多い。大問1問にかけられる時間が20分だとすると、この問題では小問1問にかけられる時間は2分となる。なのでペンを止めて考え込む時間はおそらく無いし、またどれも計算量はそれほど多くなく難問でもないので、これくらいは問題を見た時にどうやれば解答まで辿り着けるかがぱっと思いつくようにしておいて欲しい。
第2問 力学 斜面での運動 摩擦 衝突
難易度は普通。物体が斜面を滑り、別の物体に衝突し、その後までの二物体の運動を考察する問題。(1)~(5)は基礎の問題なので、最低限これらは解けていて欲しい。(6)以降は、(5)までに計算した事を使っていけば解けるはずだが、IIIとIVはBと壁との反発係数が異なる、それぞれに独立した問題のため、どちらかがわからなくてももう片方には支障が出ない。なので、もしIIIかIVのどちらかで詰まったとしてももう片方はできないかどうかはしっかりと考えよう。
第3問 電磁気 コンデンサーを含む回路
難易度は普通。複数のスイッチとコンデンサーを含む回路について考察する問題。こういった問題のセオリーは、①電荷保存則、②キルヒホッフの法則、③コンデンサーの基本式(Q=CV)の三つの式をたてるという事である。(10)、(11)については、スイッチを閉じる前と閉じた後について、抵抗の左右のコンデンサーの電気量を計算するのがよいだろう。
2011年度
全体
全体的な難易度はやや高め。第2問と第3問の難易度がやや高く、この2問を完答するのは難しいだろう。第2問は(8)だけが特に難しいのに対し、第3問は全体的にコンスタントに難しいので、おそらく多くの受験生にとっては、第2問よりも第3問の方が出来ないと思う。また第4問も前半は知識問題なので、できなかった人はこの年度は燦々たる結果になったのではないかと思う。
この大学では半導体は出るので、そこをしっかりと対策して、第1問と第4問はほとんど完答と言っていい程取れば、残り第2問と第3問を出来るだけやれば合格点は取れるはずである。この年度の勝負は、第1問と第4問をどれだけ取れるか、という部分になってくると思う。
第1問 小問集
(1)は力学、万有引力の分野から、第1宇宙速度を計算する問題。
(2)は波動、凸レンズの分野から、ある条件下の像を結べるレンズの位置を計算する問題。
(3)は電磁気、コンデンサーの分野から、極板間に導体板を挿入した時の電気容量を計算する問題。
(4)は力学、浮力の分野から、物体の水面上にある部分の体積を求める問題。
(5)は、力学、モーメントの分野から、静止が崩れる時について考察する問題。
難易度は普通。小問の数も大問数が同じ2009年度と同じである。この年度は力学の大問が出ていない事からかもしれないが、5問中3問が力学の問題である。大問1問あたりにかけられる時間を15分とすると小問1問には3分かけられるので、少しじっくり考えてでもここはしっかり取っていきたい所である。
第2問 電磁気 電荷の運動
難易度はやや高め。磁場中に発射された電荷の運動を考察させる問題。反発係数eで壁に衝突したりなど、電磁気の問題と言ってもかなり力学に近い所がある。設定としても珍しいもののため、戸惑った人も多いのではないだろうか。(7)まではなんとか解けるかもしれないが、(8)が解けた人はおそらくほとんどいないのではないかと思う。赤本の解答を見ればわかるが、途中観測者の系を変えるなど、相当の実力が無いとできない事をやっているので、正直これは捨てて良い所だと思う。
第3問 熱力学 気体分子運動論
難易度はやや高め。断熱膨張について、気体分子という観点から考察を加える問題。第2問は(8)のみが難しかったが、この問題は真ん中あたりから難しくなってきて、こちらの方が解けないという人も多いと思う。そもそも気体分子運動論という分野を苦手としている人が多いので、こういった問題が出るという事も踏まえてしっかり対策をしていこう。
第4問 電磁気 半導体 ダイオード
難易度は普通。前半は半導体ダイオードの仕組みについて、穴埋めで考察し、後半はダイオードを含む回路について考察する問題。
前半は一応考えてもある程度は解けるというもののほとんど知識問題であり、この大学は半導体ダイオードを好んで出すと知っていれば解けるだろうが、一般の受験生は抜け落ちている事が多い部分である。傾向を読み、しっかり対策しておこう。
後半は、ダイオードの性質も問題文中に書かれているので、前半があまり解けなかった人でも手が出せる部分だと思う。こういった問題の解き方は、ダイオードの部分を一旦導線とみなし、そうしたらそこにはどの向きに電流が流れるか、という事を考え、それがダイオードの向きと一致するかどうか、というプロセスを踏むとよい。もし一致しなかった場合は、流れない、という事である。
2010年度
全体
全体的な難易度は例年通り。第2問、第4問をやや高めと設定しているが、第2問は完答が難しいという意味でその人の実力によって半分なり、8割なりでき方が変わってくると思う。一方第4問は小問が無い記述式で、記述力のある人はおそらく満点をとってくるだろうし、そうでない人はかなり減点されてしまい、ほとんど満点か0点か、といった所だと思う。
第4問のような問題はあまり出題されないのであまり対策ができていなく、ここはほとんど取れない人が多いかもしれないが、その分第1問、第3問、第5問は完答する事は決して難しくないと思うし、残りはなんとか部分点を取れば全体として7割、8割くらいは取れるのではないかと思う。
第1問 小問集
(1)は波動、凸レンズの分野から、レンズの焦点距離を求める問題。
(2)は波動、ドップラー効果の分野から、観測者が聞く音の振動数を求める問題。
(3)は電磁気、クーロンの法則の分野から、クーロン力の大きさを求める問題。
(4)は力学、モーメントの分野から、静止が崩れる時について考察する問題。
難易度は普通。(2)のドップラー効果の問題が、音源が動くだけならともかく、風も吹いているという所が少し難しいかもしれない。風も考慮に入れたドップラー効果の公式を覚えている人ならともかく、そうでない人が大半だと思うが、そういう人はどうするか。ドップラー効果の公式の証明をする時のように実際に波を書いてみて考えても良い。もう一つのやり方としては、風とともに動く系から見ると風は無く音源も観測者も動いている状態となり、こちらは公式を覚えていると思うので解ける。風を含むドップラー効果にはこのようなやり方があるが、公式を使える後者の方がやりやすいし早いと思う。風を含む公式を覚えるなり、その場で考えるなりは自由だが、大問で考察させられた時に解けるのは後者なので、自分で考えるように、できれば後に説明したやり方でできるようになっていて欲しい。(1)、(3)、(4)は基本なので、全てミス無く取りたい。
第2問 力学 ばね 単振動
難易度はやや高め。鉛直状態でばねの上に物体を載せ、その物体の運動を考察する問題。内容の難易度は高いものの小問数が多く、その分誘導がしっかりしているのである程度は進める事ができると思う。しかし大問数が5問なので、1問あたりにかけられる時間が12分だとすると、これを12分で全て解くのは少し厳しいかもしれない。時間で見切りをつけて先へ進むのがよいだろう。
第3問 熱力学 等温変化 定圧変化
難易度は普通。ピストンで閉じ込められた気体の等温変化、定圧変化について考察する問題。内容自体は難しくはないものの式が多少複雑になるので、計算ミスの無いように注意して計算しよう。(6)は、そもそも単原子分子理想気体の場合定積モル比熱が![]() 、定圧モル比熱が
、定圧モル比熱が![]() となる事は知っていると思うので、答えはRと計算しなくてもすぐに出てしまう。なのでもし途中で解けなくなっても問題文は最後まで読んで、(6)だけは取るようにしよう。
となる事は知っていると思うので、答えはRと計算しなくてもすぐに出てしまう。なのでもし途中で解けなくなっても問題文は最後まで読んで、(6)だけは取るようにしよう。
第4問 熱力学 比熱
難易度はやや高め。プロペラが回ることによって上昇する水の温度を計算する問題。ここ5年間で唯一の、解答までの道筋も求められる記述式の問題である。問題自体は物体の位置エネルギーの変化が水に与えられた熱量という単純なものだが、それでは簡単すぎるためおそらくそのプロセスや、途中のエネルギー損失が無い(無視できる)という事、物体の運動エネルギーについては考慮しない事などを明確に記述しなければならないと思う。
第5問 電磁気 磁場中の電荷 等速円運動
難易度はやや低め。磁場中を運動する電荷の運動について考察する問題。(1)(2)はグラフを描き、それを見ながら(3)に答える、という構成になっている。
(1)でポイントになるのは、磁場から電荷に働くローレンツ力は必ず速度に垂直な方向なので、磁場は絶対に電荷に仕事をしない、つまり磁場が原因では電荷の速度は変化しない、という事である。
(2)は、電荷の磁場に平行な方向の成分が0であるという事から、等速円運動だとわかる。これはおそらくできるだろう。ちなみにこれが0ではなかった場合は、らせん運動となる。
(3)は、(2)のグラフの一点の座標を読み取るだけなので(2)が出来れば難無く解けると思う。この第5問は、全て解けていて欲しい。第2問、第4問も解ける人は全て解けるだろうし、そうでない人も8割くらいは解ける状態にしておこう。残りを第3問で稼ぐ、といった作戦でよいと思う。
2009年度
全体
全体的な難易度は例年通り。第4問の難易度が少し高く、おそらく半導体についてある程度勉強した人でも少し詰まる部分があると思う。なので、その分は他でカバーしなければならない。第1問の小問集にこれは少し難しいと思われる物は無かったので、ここは完答して欲しい。
第1問 小問集
(1)は力学、運動量と力積の分野から、力積と時間から平均の力を計算する問題。
(2)は電磁気、クーロンの法則の分野から、クーロン力の大きさを計算する問題。
(3)は波動、音波の分野から、閉管が共鳴する時の管の長さを計算する問題。
(4)は波動、凸レンズの分野から、レンズの焦点距離を計算する問題。
(5)は熱力学、理想気体の分野から、ボイル・シャルルの法則で温度を計算する問題。
難易度はやや低め。どれも基礎中の基礎で、全て解けていて欲しい問題である。(1)は2008年度に数値が変わっただけの全く同じ問題が出題されているので、必ず解けなければならないと思う。(2)はクーロンの比例定数が与えられていないが、文章中にある条件下での力の大きさが書いてある。距離が2倍になるとクーロン力はどうなるか、電荷が2倍になるとどうなるか、という事を考えて解こう。第1問は10分以内に解きたい。
第2問 力学 定滑車 動滑車
難易度は普通。定滑車と動滑車に繋がれた二つの物体の運動について考察する問題。まず前半で、動滑車の性質について説明している。それを踏まえた上で後半の2物体の問題へと移っているので、誘導はかなりしっかりしている方だと思う。完答できれば後が楽になるが、時間的に厳しいという人もいるだろう。それでも最低限(6)か(7)くらいまでは解けて欲しい。
第3問 電磁気 半導体
難易度はやや高め。半導体について考察する問題。文章の穴埋め式となっていて、誘導こそしっかりしているものの、内容のレベルは少し高く、難しい部類に入ると思う。この大学が好む半導体についての問題である。これも普段あまり触れる問題ではないので、この大学が半導体を出すのが好きという事を踏まえた上で対策をしていないとなかなか厳しいのではないかと思う。
第4問 波動 正弦波
難易度はやや低め。波の波形とある位置の変異の時間変化のグラフを基に考察する問題。しばしば波の波形(変異-位置のグラフ)とある位置における変異の時間変化(変異-時間のグラフ)を混同している人がいるが、そういう人にとっては意味のわからない問題だったのではないかと思う。(3)は理由も記述式で書かなければならないので、多少記述力も問われると思う。わかっている人ならば、10分以内で完答できる問題だと思う。ここはぜひ完答して欲しい。
2008年度
全体
全体的な難易度はやや高め。第2問のレベルがかなり高いため、第1問と第3問はほぼ完答に近い精度が求められると思う。その上で第2問にも半分弱手をつけて初めて合格点の上をいく事ができるといった所だろうか。最低でも第1問と第3問は8割、第2問は④までくらいは解けないと、合格点を取る事は厳しいだろう。
第1問 小問集
(1)は波動、ドップラー効果の範囲から、うなりの回数を計算する問題。
(2)は波動、光の干渉の分野から、薄膜で光が強め合う膜の厚さを計算する問題。
(3)は熱力学、比熱の分野から、銅球の比熱を計算する問題。
(4)は力学、運動量と力積の分野から、力積と時間から平均の力を計算する問題。
(5)は力学、自由落下と衝突の分野から、小球が最高点に達するまでの時間を計算する問題。
(6)は力学、等速円運動の分野から、円運動の周期を求める問題。
(7)は電磁気、電場と電位の分野から、電荷のある位置での速度を計算する問題。
(8)は電磁気、抵抗率の分野から、送電線の消費電力を計算する問題。
(9)は電磁気、コンデンサーの分野から、ある操作をした後の極板間電位差を計算する問題。
(10)は熱力学、理想気体の分野から、分圧を用いて全圧を計算する問題。
難易度は普通。これといって難しい問題は無く、また小問集なので1つできない問題があっても他に影響を与えないので、得点が取りやすい部分だと思う。力学、電磁気、波動、熱力学の問題がバランス良く出ている。全て教科書に書いてあるような基礎的な内容なので、全て取りたい。
第2問 ばね 単振動
難易度は高い。3つのばねに挟まれた2つの物体の運動について考察する問題。(1)は力の釣り合いで、(2)はAのみの単振動なので割と簡単に解けるが、(3)以降はAもBもともに動き、少し難しくなっている。時間的な問題も相まって、ここから先が解ける人はそうそういないのではないかと思う。(2)か(3)くらいまで解いて一旦見切りをつけて第3問に進む方がよいと思う。
第3問 電磁気 磁場中の導体棒 摩擦
難易度は普通。磁場中におかれた導体棒の運動について考察する問題。導体棒とレールの間に摩擦があるという事は少し珍しいなと思うが、他はよく見る典型問題である。摩擦という要素が加わったからといって特別難易度が上がるわけではないと思うので、一つ一つ慎重に解こう。