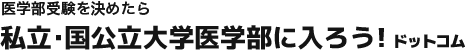第18回:酸と塩基(5)
今回は、逆滴定・二段滴定という、少し応用的な中和滴定を説明します。今回紹介する滴定の方法は、医学部の入試にもよく出されるものですから、しっかりと理解して、使いこなせるようにしてください。
1)逆滴定
アンモニアや二酸化炭素のように、気体の塩基や酸の物質量を中和滴定で調べようとしたとき、これを第17回で紹介した方法で行うわけにはいきません。だって、コニカルビーカーやビュレットに気体を入れるわけにはいきませんよね。入れてもすぐにどこかへ飛んで行ってしまいます。
そこで、このような気体の塩基や酸の物質量を測定するには、濃度の分かっている酸や塩基の水溶液の中に吹き込んで完全に中和反応させた後、残った酸や塩基の物質量を調べるという方法を取ります。
たとえば、気体のHClがnmolあったとして、これを0.1 molのNaOHを含む水溶液に吸収させたとします。
そのあと、残ったNaOHの物質量を中和滴定で測定したところ、0.05mol残っていたとします。そうすると、nmolのHClと反応したNaOHは0.1-0.05 mol=0.05 mol ですね。
ここで、HClとNaOHはともに1価の酸と塩基ですから、1:1の割合で反応します。
したがって、HClの物質量:反応したNaOHの物質量= n:0.05 = 1:1 が成立し、n=0.05molとわかるわけです。
ここまでが基本です。では、次に、もう少し文字を複雑にしてみましょう。
例題
気体中に含まれるHClの物質量を、以下の手順で測定した。
- 実験I
- HClを含む気体をa mol/ℓ のNaOH水溶液 v1 mℓに完全に吸収させた。
- 実験II
- NaOH水溶液中に残ったNaOHの物質量を測定するため、b mol/ℓ のHCl水溶液を用いて中和滴定したところ、中和点までにv2 mℓを必要とした。
問.もとの気体に含まれるHClの物質量を、与えられた文字で表しなさい。
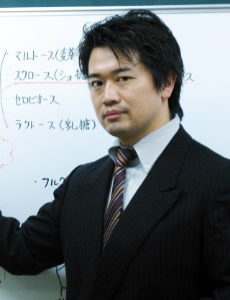
平野 晃康
株式会社CMP代表取締役
私立大学医学部に入ろう.COM管理人
大学受験アナリスト・予備校講師
昭和53年生まれ、予備校講師歴13年、大学院生の頃から予備校講師として化学・数学を主体に教鞭を取る。名古屋セミナーグループ医進サクセス室長を経て、株式会社CMPを設立、医学部受験情報を配信するメディアサイト私立大学医学部に入ろう.COMを立ち上げる傍ら、朝日新聞社・大学通信・ルックデータ出版などのコラム寄稿・取材などを行う。